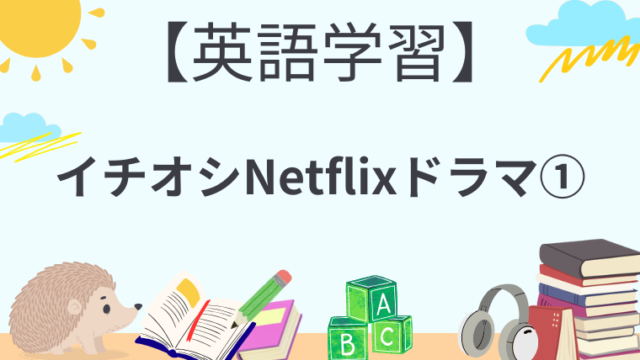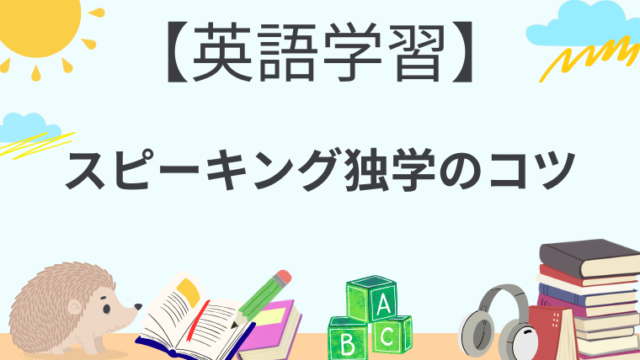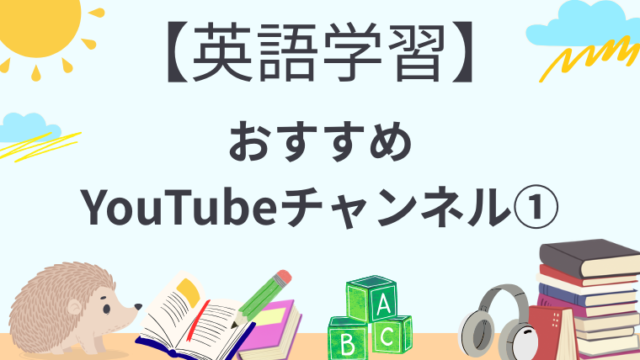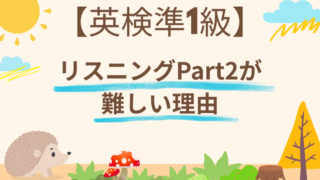【英検準1級】リーディングはなぜ難しいのか?
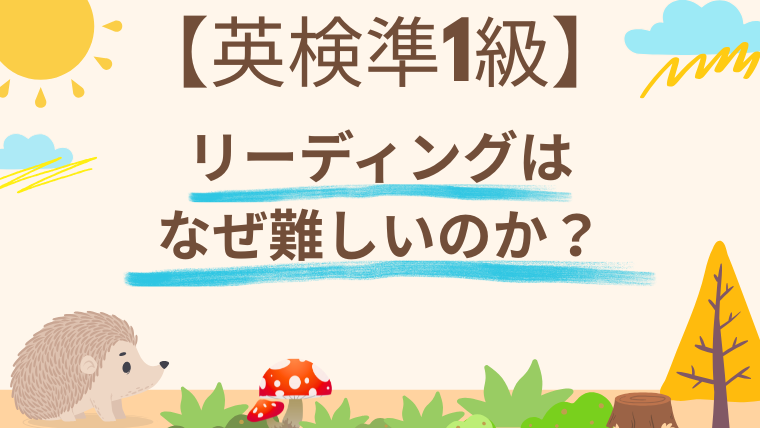

こんにちは、もち丸です。
英検1級合格・TOEIC960点取得などの経験を活かして、英語講師をしています。
このブログでは、主に英語資格試験の対策・勉強法などを紹介しています。
英検の指導をしていると、
「2級は独学で合格できたのに、準1級は独学では手も足も出ない・・・。」
というお悩みを聞くことが多いです。
個人的にも、2級と準1級とではそのレベルにかなりの差があると思っています。
そこでこの記事では、
準1級のリーディング問題がなぜ難しいのか、私なりの見解をお伝えしたいと思います。
2級の難易度については、こちら↓↓
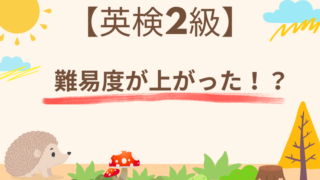
英検準1級のリーディング問題が難しい理由
準1級のリーディングが難しく感じる理由として、主に以下が考えられます。
- 語彙のレベルが高い
- 文構造が複雑
- 抽象的な表現が多い
- 長文の内容が専門的
- 設問が難しい
それぞれの理由について詳しく解説していきます↓↓
①語彙のレベルが高い
まず、最初の理由が「語彙のレベルが非常に高い」ということです。
準1級では、専門的な単語や難しい熟語が容赦なく出題されます。
そもそも2級までだと、中学校や高校で習ったような語彙で答えられることが多いです。
大学受験で必須の単語がほとんどなので、多くの高校生が使用している「システム英単語」や「英単語ターゲット」を完璧にしていれば語彙でつまずくことはまずないでしょう。
ところが、準1級の単語は難しいものが本当に多いです。
大学受験でいうと難関大学で出題されるような単語や熟語がバンバン出てきます。
それに対応できる語彙力が無いと、リーディング問題を解くのは厳しいです。
特にリーディング問題のPart1の語彙は、他のリーディング問題や技能に比べても高度な単熟語が多く出題されます。
「こんな語彙、ネイティブは一体いつ使うんだ!?」とツッコミたくなるような言葉が選択肢に並んでいます。
そのため、中学校や高校で学習するような語彙範囲では足りないので、準1級合格のためには新たにボキャブラリーを増やしていく必要があります。
ちなみに、2級から準1級受験にあたって必要な語数はだいたい+2000語です。
「でる順パス単」や「単熟語EX」などの準1級専用の単語帳を使って高レベルな語彙に対応できるようにしておきましょう。
準1級は難しい語彙が多く出題される。
準1級用の単語帳を使うなどして、語彙力を身に付けておく必要がある。
②文構造が複雑
語彙に加えて、リーディング問題が難しくなっている理由が「文法」です。
準1級の英文の特徴として、1つの文章が長く文構造を捉えにくいというのがあります。
準1級の英文は、挿入があったり、関係代名詞やら分詞やらの修飾がたくさんあったりして、とかく1文が長くなりがちです。
2級の文章と比べると、まあ本当に長いです。
1文が3行にまたがっている、なんていうのもザラにあります。
当然ながら、全体の文章量も非常に多いのでゆっくり読んでいる暇はありません。
そして、複雑な文法がいろいろ使われているので、文章の骨格である「SV」=「主語・動詞」を見つけるのが難しくなります。
その結果、結局英文を正確に和訳することができず、文意を把握できないということがあります。
もしくは、英文の構造を掴むのに時間を掛け過ぎてしまい、試験時間が足りなくなってしまったりします。
対策としては、まずは、文法をしっかりと理解しておくことが大事です。
それから、精読の練習をして文構造を正しく解釈できるようにしておきましょう。
さらに、準1級レベルの長文問題を多くこなして、読解に慣れておくようにしましょう。
1文が長いので、文構造を正確に理解し正しく日本語訳できることが大切。
文法の知識を定着させ、精読と長文読解の訓練を繰り返し行いましょう。
③抽象的な表現が多い
準1級長文問題あるあるなのが、「抽象的な表現が多く、文意が分かりにくい」ことです。
準1級長文は、
そもそも難しい語彙が使われているために、言い方が具体的でないものが多いです。
例えば、
“make a long-term relationship”「長期的な関係を作る」が、
“establish sustained contact”「持続的な接触を確立する」と表現されていたり。
こういった抽象的な表現に慣れていないと、準1級長文の主旨を掴むことは難しいです。
この抽象表現に慣れるためには、
筆者の主張や前後の文脈を頼りに、具体的な和訳表現に置き換えていくことが大事です。
例えば「持続的な接触を確立する」だと、
「持続的な」→「長期の、ずっと続く」
「接触」→「つながり、交流、関わり」
「確立する」→「築く、作る」
と言い換えることができます。
「持続的な接触を確立する」=「長く続くつながりを作る」だと解釈できれば、かなり文章を理解しやすくなります。
そして、具体的に言い換えた内容は常に頭の中でイメージしておくことが大事です。
そうすることで、難しい内容の英文でも文脈を追いやすくなります。

準1級長文の抽象表現を理解するためには、
「抽象→具体」に和訳を言い換えて、その内容をイメージしながら読む。
④長文の内容が専門的
そもそも長文のテーマが難しいというのも、準1級リーディングのレベルが高い理由です。
準1級の長文の出題テーマは、
「環境」「教育」「歴史」「科学」「医療」「政治」「芸術」などなど、様々です。
そしてこういったジャンルの話が専門的な内容で論じられています。
一般にはなじみが薄い話がほとんどで、しかもそれらが難しい表現で語られています。
かなり高度な内容なので、背景知識があるかどうかで理解度が変わってきたりします。
もちろん、背景知識が無かったとしても設問にはちゃんと解答できる作りになっています。
こういった難解な長文を試験中の限られた時間内に読んで理解しなければならないので、準1級のリーディングは相当レベルが高いです。
この長文のレベルに対応するために、ある程度社会問題に慣れておくといいです。
普段からラジオを聴いたり新聞を読んだりして時事問題に積極的に触れておきましょう。
可能であれば、日本語ではなく英語で聴いたり読んだりできると良いです。
そして、
頻出テーマに関連する語彙で準1級の出題範囲であるものは、必ず押さえておきましょう。
例えば、「環境」に関連するワードであれば、contamination(汚染)/ conservation(保護)/ ecosystem(生態系)/ deforestation(森林伐採)/ habitat(生息地)といった単語は長文問題に出てきても瞬時に意味を答えられるようにしておきたいところです。
準1級の長文問題はなじみのない難しい内容が多い。
頻出テーマに関連する話や語彙には慣れておくようにしましょう。
⑤設問が難しい
問題文以外の点でいうと、設問の種類が難しいというのが準1級リーディングの特徴です。
準1級の長文では、推論型の設問がよく出題されます。
推論型とは、本文の内容を根拠にして、文中にはっきり書かれていないけれども読み取ることができる情報として正しいものを選ぶという種類の問題です。
「選択肢の情報が文中に直接明示されているわけではない。」というのが推論型の難しいところです。
例えば、以下のような問題が推論型にあたります。
括弧内の文章から推測できる情報として最も良いのは選択肢①~④のうちどれでしょうか?
「若い世代では本を読む習慣が無くなってきていると、多くの人が思っている。ところが研究によると、最近の若者は上の世代の人々に比べると、より多くのオンライン記事や電子書籍を読んでいることが分かった。」
①若者は本を読むことが嫌いだ。
②本を読む習慣は消えたわけではなく、読む形式が変わった。
③オンライン読書は上の世代の人々にとって危険だ。
④若者より、上の世代の人々の方がはるかに読書量が多い。
答えは、②「本を読む習慣は消えたわけではなく、読む形式が変わった。」です。
選択肢の情報「本を読む習慣は消えていない」や「読む形式が変わった」といったことは一言も問題文に書かれていません。
しかし問題文から、若い世代では「従来の紙の本→オンライン記事や電子書籍」に読書の形が変わったということが読み取れます。
このように選択肢の情報が文中に明確に書かれているわけではないので、
問題文を正しく解釈し、そこから得られる情報を自分で推測して答えなければいけません。
準1級になるとこの推論型の問題が多く、また英語で読んで理解しなければならないので、相当な読解力が必要となってきます。
推論型の問題への対策としては、まず英文を正しく解釈できる力が必須です。
そのために語彙や文法は徹底して強化しておくことが大事です。
また、英文をただ追いかけるのではなく「その文章や段落が最も主張したいことは何か?」を常に考えながら問題文の要旨を掴んでいくようにしましょう。
準1級の設問は推論型が多い。
英文を正確に解釈し、その内容から分かる情報を推測できる読解力が必須。
まとめ
準1級のリーディング問題がどうして難しいのかについて、個人的な見解をご紹介しました。
- 出題される単語や熟語が難しい
- 1文が長く英文の構造が複雑
- 長文のテーマが専門的で、内容の理解が大変
- 設問の内容が難しく、一筋縄では解けない
準1級リーディングは2級までの問題と比べると、かなりレベルが上がって難しくなります。
特にリーディングは、他の技能と比較しても語彙や文法が難しいので、時間をかけて念入りに対策するようにしましょう。
以上、このブログの内容が少しでも英検準1級対策の参考になれば幸いです。